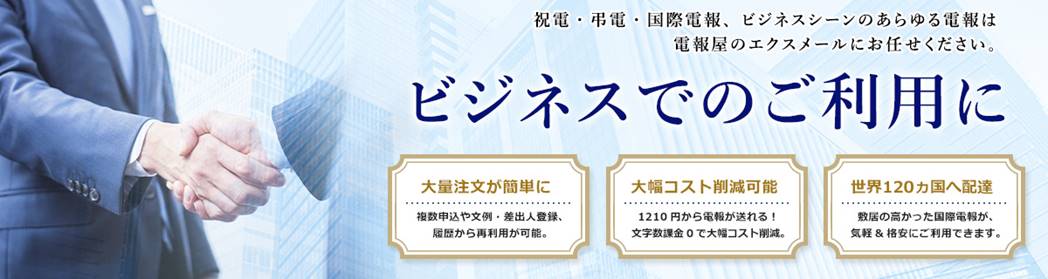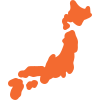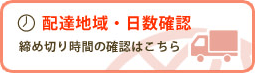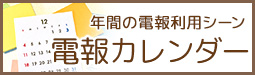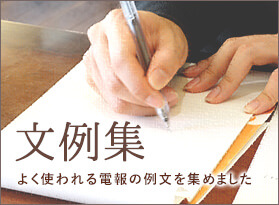会社から弔電が届いた場合【お礼・お返しのマナー】を解説

故人もしくは親族の方がお世話になっている会社からの弔電ですから、受け取った側としてはきちんとマナーをもって対応したいところです。
しかし「弔電にお礼の品は必要なのか」「お返しの相場が分からない」などとお悩みの方も多いでしょう。
そこで今回は、「会社からの弔電」に対するお礼・お返しのマナーについて解説します。
目次
会社からの弔電に対するお礼の方法、お返しの相場
「会社から弔電を受け取った」となると、一層マナーの存在が気になるところです。喪主もしくは親族の勤め先や取引先から弔電を頂いたのであれば、今後のビジネスの関係においても重要なお礼となります。
また「香典」や「供物」を頂いた場合は、特にお礼やお返しが重要になるため、今後のビジネスの関係や信頼を損なわないためにも、弔電への返礼のマナーはきちんと把握しておきましょう。
ここでは、会社から受け取った弔電の内容別に、お礼・お返しのマナーについて解説します。
弔電のみの場合:お礼の言葉を伝える
まず、「弔電のみを受け取った」という場合は、基本的にお礼の品物を用意する必要はありません。お礼の品物を贈ると、かえって相手に気を遣わせてしまいますので、弔電に対するお礼の気持ちのみを相手に伝えましょう。正式なお礼の方法としては、相手方に出向いて直接伝えるのが一番良いですが、近年では「お礼状」を送る方法が一般的となっています。
ただし、勤務先の会社から福利厚生として手配された弔電に対しては、手配してくださった部署の方に口頭でお礼を言うと良いでしょう。
また、これは会社の制度にもよるのですが、家族が亡くなったときは忌引き休暇を取得することがあります。その場合は休暇明けに出勤した際、上司や職場の同僚への「復帰の挨拶」と「休んでいた間にフォローをしてくれたことへの感謝」とあわせて、「弔電のお礼」も伝えるようにしましょう。
お礼状を送る場合は、葬儀から1週間以内を目安にして送ることが重要です。
お礼状には、弔電を受け取ったことや葬儀を無事に終えたこと、故人に代わって生前お世話になったことへの感謝などを書いて送るのが一般的です。
ただし、お礼状は略式になりますので、文末に「略式ながら書中をもちまして謹んでお礼申し上げます」などの一言を添えましょう。
また、お礼状を送った後でも、直接会う機会があった際は、口頭でお礼を伝えるとより丁寧です。
弔電と供花・香典などの場合:返礼品を用意
次に、「会社から弔電と共に香典や供物、供花などを一緒に受け取った」という場合は、お返しの品物(返礼品)を用意しましょう。返礼品の金額は、受け取った物のおよそ3分の1から半額相当のものを選ぶのが一般的です。送るタイミングについては、忌明け(仏式では四十九日法要が終わった後)に送るようにしましょう
ただし、弔電のみを受け取った場合と同様に、勤務先の会社から福利厚生として弔電が手配された場合は、弔電などを手配してくれた部署の方へお礼を言いましょう。
一方で、「会社から」ではなく「所属部署の社員有志から供花などを頂いた」という場合は、何らかのお返しが必要になります。この場合、部署全体に対してお返しをするか、部署の一人ひとりにお返しをするかについては、会社の慣習などに従って対応すると良いでしょう。
近年人気のある、プリザーブドフラワーやお線香付きの弔電などを会社から頂いた場合は、お返しをしなくてもマナー違反ではありません。
とは言え心苦しいのでお返しをしたいという方は、香典などを一緒に受け取ったときと同じように、頂いたギフトの3分の1から半値ほどの品物をお返しすると良いでしょう。
葬儀が「家族葬」であった場合の弔電のマナーについては、下記のコラムで詳しくご紹介していますのでぜひ合わせてご覧ください。
弔電に対するお礼のマナー
最後に、弔電に対するお礼の基本的なマナーについて解説します。弔電のお礼は葬儀後1週間以内に贈る
弔電のお礼は、葬儀を終えてから1週間以内に送ることを心がけましょう。葬儀の直後は心身ともに大変疲れがたまりますので無理は禁物ですが、弔電を受け取ったことと、葬儀が滞りなく終了したことを知らせる意味もありますので、お礼はなるべく早い方が良いでしょう。
メールや電話のみでのお礼はマナー違反になる?
弔電に対する正式なお礼は、相手方に直接出向いて直接伝えること基本ですが、近年ではお礼状などでお礼をしてもマナー違反にはなりません。お礼状も略式となりますので、文中で一言「略儀ながら」と添えましょう。親しいお取引先や担当者の方からの弔電であれば、まずは電話でお礼を伝え、故人について話をしたり、改めて挨拶へお伺いする日程について相談するのも良いでしょう。
現代では会社の考え方や、会社と個人との関わり方、社内での関係性も多様化しています。
日常的にチャットアプリやメールで連絡を取り合う間柄であれば、電話やメールでお礼を伝えることもあります。
大事なことは頂いた弔電に対して、感謝の気持ちを伝えることです。形式に拘り過ぎず、それぞれの状況や関係性に応じて、柔軟に判断しましょう。
ただし、取引先からの弔電など、会社同士の関わりが出てくるケースにおいては、SNS、メッセージアプリなどだけで済ませることは基本的に避けた方がよいでしょう。
いくら利便性があるといっても、弔電という形式に則って送られたメッセージに対しては、あまりにも簡略的と捉えられることがあります。
弔電に対するお礼の基本的なマナーについては下記のコラムで詳しく解説しています。お礼状の文例もご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ:会社からの弔電にはマナーを守って対応しましょう
会社から弔電を受け取った場合は、適切な方法で返礼(お礼・お返し)をすることが重要です。品物(返礼品)の有無は、弔電の内容次第で変える必要がありますが、マナーに従ってお礼を伝えることで、より良い関係性を築くことができるでしょう。
電報屋のエクスメールでは、電報に関するお悩み・ご相談もお受けしております。
電報と一緒にギフトを贈りたい、電報の送り方やマナーが分からず不安という方もお気軽にご相談ください。
電報に関するご相談はこちら
弔電・お悔やみ電報におすすめの商品やメッセージの文例を下記のページでご案内しています。
弔電・お悔やみ電報はこちら
3万社様がコスト削減に成功!法人での電報利用はエクスメールにお任せください!エクスメールが選ばれる理由や料金等については下記のページで詳しくご案内しています。
法人で電報ご利用される方はこちら
弔電・お悔やみ電報におすすめの商品やメッセージの文例を下記のページでご案内しています。
弔電・お悔やみ電報はこちら
3万社様がコスト削減に成功!法人での電報利用はエクスメールにお任せください!エクスメールが選ばれる理由や料金等については下記のページで詳しくご案内しています。
法人で電報ご利用される方はこちら
電報のお申し込みは電報屋のエクスメール!
エクスメールは、世界中のどこからでも、
日本と世界の主要120ヵ国へ、速やかに電報をお届けします。
お申し込みはこちらから
エクスメールは、世界中のどこからでも、
日本と世界の主要120ヵ国へ、速やかに電報をお届けします。
お申し込みはこちらから